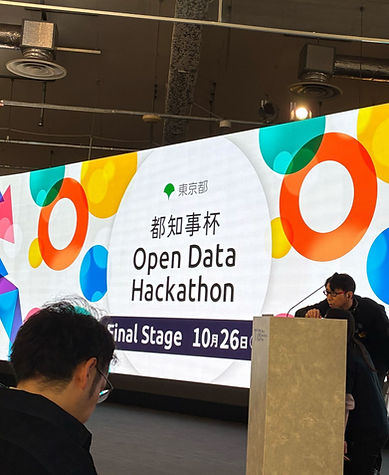(東京科学大学 西田佳史研究室)
生活セントリック
デザインラボ
生活を深く理解することで「手に負えない」を「手に負える」へ変化させる生活セントリックデザイン
人間の機能が変化し続けることが当たり前の時代が到来しています。人間の計測・分析、システムデザイン、サービスにおけるUX/UIデザイン、安全工学、複雑システム科学などの従来から人間中心を扱っていたあらゆる領域において、時間変化する人を扱う新たな方法論が求められています。
生活セントリックデザインラボでは、IoT・ロボティクス、人工知能、ビッグデータを活用し、心身機能が変化し続けても、その変化を飲み込み(織り込み済みにし)、その人の生活を安全で社会参加が高い状態へ持続的にデザイン可能にする科学技術領域(パラダイム)の創造を目指しています。
研究機関、行政機関、リビングラボ(実務者)などとの多職種連携によって、子どもや高齢者の生活支援・傷害予防などの社会課題に対し、状況という系を扱う数理技術、ビヘービア・ベースのセンシング技術、個人長期間計測による非エルゴ―ド的人間理解技術、生理・行動・心理・社会モデルを統合した生活モデリング・シミュレーション技術、困難を生み出す背景理由(社会的決定要因等)の考慮によって一段深く行動変容を生み出すエンパワメント技術、などの新たな技術を開拓しながら社会インパクト駆動型で進めています。




最近のニュース
新B4・大学院むけ研究室の説明・見学会
一緒に社会を変える研究をしませんか? 新B4研究室配属・大学院入試等の準備のため研究室の説明や見学を希望する人は、以下より申し込んでください。




社会実装・地域連携プロジェクト(小児安全)
Be the change for childhood safety
東京都、セーフキッズジャパン、産業技術総合研究所等と進めている子供の安全に関する多職種連携の社会実装プロジェクト。

受賞のお知らせ(2026/2/20)
修士2年の半田さんの下記の発表に関して、計測自動制御学会・UDXワークショップ2026でUDX賞を受賞しました。
-
半田慧, 野村彩乃, 栗林詩歩未, 北村光司, 河合恒, 西田佳史, "フレイル高齢者支援を目的とした生活環境における小さな形状変化が身体保持性に与える効果の解析," 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025予稿集, pp. 2A1-A05 , 2025




日本神経理学療法学会, 公衆衛生の国際会議(APHA), 老年医学の国際会議 (GSA), マルチメディアに関する国際会議で研究発表。
-
Mikiko Oono, Ryo Shinozawa, Yoshifumi Nishida, Satoko Hotta, "Development and Evaluation of a System to Propagate Micro-Happiness among People with Dementia," Proc. of the 2025 International Conference on Smart Multimedia (ICSM), 2025 (Paris, France)
-
Satoru Handa, Ayano Nomura, Shihomi Kuribayashi, Koji Kitamura, Hisashi Kawai, Yoshifumi Nishida, "Effect of Small Retrofitting Changes to Daily Living Environments for Supporting the Bodies of Frail Older Adults," Proc. of 2025 Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America (GSA), 2025 (Boston, USA)
-
川崎 詩歩未 , 野村 彩乃, 半田 慧,北村 光司 ,河合 恒,西田 佳史, "家具の材質の違いが高齢者の前頭前野血流量および主観的感覚に与える影響とその類型化, "第23回日本神経理学療法学会学術大会抄録集, p.402, eP33-4, 2025 (石川県立音楽堂)
-
Satoshi Inagaki, Noki Sano, Mikiko Oono, Yuki Hashimoto, Tatsuhiro Yamanaka, Yoshifumi Nishida, "Computer-Vision-Based Home Visit Investigation on the Distance Moved by Young Children’s Turnover during Sleep for Sleep Safety Research," Proc. of the 2025 APHA (American Public Health Association) Annual Meeting and Expo, 2025 (Washington D.C., USA)


2025/10 センサーに関する国際会議・傷害予防に関する国際会議での研究発表
カナダで開催されたセンサに関する国際会議 IEEE Sensors 2025、米国で開催された傷害予防の実務家が集う国際会議(PrevCon)で睡眠環境調査、窒息予防の研究の結果を発表しました。
-
Satoshi Inagaki, Naoki Sano, Mikiko Oono, Yuki Hashimoto, Tatsuhiro Yamanaka, Yoshifumi Nishida,, "The first home-visit investigation on infants' sleep environments in Japan using a bedding hardness tester," Safe Kids Worldwide's Injury Prevention Convention (PrevCon), 2025 (Washington D.C., US)
-
Haruka Tokutomi, Kan Takagi, Mikiko Oono, Koji Kitamura, Tatsuhiro Yamanaka, Yuki Hashimoto, Yoshifumi Nishida, "New Method for Evaluating the Deformability of Foods to Determine Their Choking Risk to Infants and Young Children", Proc. of IEEE Sensors 2025, Oct. 20 2025 (Vancouver, Canada)
-
Satoshi Inagaki, Naoki Sano, Mikiko Oono, Yuki Hashimoto, Tatsuhiro Yamanaka, Yoshifumi Nishida, "Development of a Vision-Based System for Analyzing Sleep Behavior of Infants and Young Children in the Home Environment," Proc. of IEEE Sensors 2025, Oct. 20 2025 (Vancouver, Canada)



傷害予防コミュニティ連携 (2025/10/12)
傷害予防の地域実装(CBPR)進めている長崎県大村市のLove&Safetyおおむらのフェスタに参加し、窒息予防技術の紹介を行いました。


2025/10 研究発表(転倒予防に関する会議、人間情報処理に関する国際会議)
-
半田慧, 野村彩乃, 栗林詩歩未, 北村光司, 河合恒, 西田佳史, “立位時の安全と安心に寄与する家具の小さなデザイン評価:脳血流計と行動計測センサを用いた安全性と嫌悪感の総合評価,” 日本転倒予防学会第12回学術集会抄録集, pp. 140, 2025
-
Naoki Nozaki, Yuya Kawabe, Mikiko Oono, Koji Kitamura, Tatsuhiro Yamanaka, Yoshifumi Nishida, “Three-Dimensional Situational Awareness for Everyday Safety: Integration of Epidemiological Data and Three-Dimensional Spatial and Behavioral Data.” Proc. of the IEEE International Conference on System, Man, and Cybernetics, pp.4875-4881, 2025 (Austria Center Wien, Austria)


受賞のお知らせ(2025/9/4)
橋本優生助教が、体温調節能力の拡張を実現する能動的発汗制御技術の基礎研究で、末松賞「革新的価値創造の基礎と展開」を受賞しました。
川崎ウェルテックPJの紹介動画(2024/9)
川崎市、産業技術総合研究所との共同プロジェクト「川崎ウェルテック」が2021/8/31からスタートしました。最新の成果を盛り込んだ動画に更新しました(2025/9)。

2025/9/3-5 研究発表(ロボティクスに関する国内会議)
東京科学大学で開催された第43回日本ロボット学会学術講演会にて、オーガナイズドセッション「生活セントリック・ロボタイゼーション」を企画しました。地域ベースのEBPM型支援機器開発、日常生活環境下での高齢者の行動理解、認知行動特性などに関する最近の成果を報告しました。
-
野村 彩乃, 半田 慧, 栗林 詩歩未, 北村 光司, 河合 恒, 西田 佳史, "日常生活で必要となる身体保持性を高める形状デザインの検証," 第43回日本ロボット学会学術講演会予稿集, pp. 1A4-01, 2025
-
半田 慧, 野村 彩乃, 栗林 詩歩未, 北村 光司, 河合 恒, 西田 佳史, 高齢者支援環境デザインの設計に向けた安全・安心 にかかわる生理量のマルチモーダル計測システム," 第43回日本ロボット学会学術講演会予稿集, pp. 2K2-04, 2025
-
添野 宏, 北村 光司, 大野 美喜子, 西田 佳史, "自治体を中心としたEBPMによる子供の傷害予防の推進," 第43回日本ロボット学会学術講演会予稿集, pp. 3H2-05, 2025
-
栗林 詩歩未, 佐野 直樹, 北村 光司, 西田 佳史, "地域共創型の介護福祉機器開発支援プラットフォーム「川崎ウェルテック」の取り組み," 第43回日本ロボット学会学術講演会予稿集, pp. 3H2-06, 2025


受賞のお知らせ(2025/8/29)
2025/8/29 東京科学大学・特別研究員(日本学術振興会・特別研究員(PD))の栗林詩歩未さんが、第24回日本生活支援工学会大会(LIFE)の下記の発表に関して、バリアフリーシステム開発財団奨励賞Finalistを受賞しました。
-
栗林詩歩未, 野村彩乃, 半田慧, 萩原裕之, 北村光司, 河合悟, 西田佳史、「脳血流変化を基にした高齢者の家具使用時の嗜好性評価の試み」、第24回日本生活支援工学会大会(LIFE), 2025

受賞のお知らせ(2025/6/29)
修士2年の半田さんの下記の発表に関して、第72回日本デザイン学会春期研究発表大会グッドプレゼンテーション賞を受賞しました。
-
半田慧, 野村彩乃, 栗林詩歩未, 北村光司, 河合恒, 西田佳史, "高齢者の生活機能変化に対応した環境デザインのための後付け可能な小さな形状の効果評価," 日本デザイン学会第72回春季研究発表大会予稿集, pp. D6-03, 2025


受賞のお知らせ(2025/6/28)
修士1年の稲垣賢さんが以下の小児保健に関する国内会議の研究発表に関して、若手奨励賞(50歳未満)を受賞しました。
-
稲垣賢、佐野直樹、大野美喜子、橋本優生、山中龍宏、西田佳史, "計測装置を用いた家庭訪問調査による乳幼児の睡眠環境の危険の理解," 小児保健研究, Vol. 84(日本小児保健協会学術集会講演集), pp. 149, 2025

シンポジウムの開催と研究成果発表(日本デザイン学会第72回春季研究発表大会, 日本小児保健協会学術集会2025)
日本小児保健協会学術集会2025にて、傷害予防エクイティに関するシンポジウムを開催し、子どもの傷害予防の研究について成果を発表しました。また、 日本デザイン学会第72回春季研究発表大会において、高齢者の自立生活支援に関する研究成果の報告をしました。
-
半田慧, 野村彩乃, 栗林詩歩未, 北村光司, 河合恒, 西田佳史, "高齢者の生活機能変化に対応した環境デザインのための後付け可能 な小さな形状の効果評価," 日本デザイン学会第72回春季研究発表大会予稿集, pp. D6-03, 2025
-
稲垣賢、佐野直樹、大野美喜子、橋本優生、山中龍宏、西田佳史, "計測装置を用いた家庭訪問調査による乳幼児の睡眠環境の危険の理解," 小児保健研究, Vol. 84(第72回日本小児保健協会学術集会講演集), pp. 149, 2025
-
西田佳史, 髙木敢、佐野直樹 、橋本優生、北村光司、山中龍宏、 "乳幼児の食物による窒息事故予防のための物理特性の基礎的理解," 小児保健研究, Vol. 84(第72回日本小児保健協会学術集会講演集), pp. 149, 2025
-
大野美喜子,本田千可子,吉川優子,三田恵子, "行動変容に頼らない予防実践のための家庭訪問マニュアル作成 , " 小児保健研究, Vol. 84(第72回日本小児保健協会学術集会講演集), pp. 163, 2025

最近の成果(論文の掲載)
高齢者の生活理解(身体保持力場計測)に関する成果が国際ジャーナル(Sensors)に掲載されました。
-
Nomura, A.; Nishida, Y. Portable Technology to Measure and Visualize Body-Supporting Force Vector Fields in Everyday Environments. Sensors 2025, 25, 3961. https://doi.org/10.3390/s25133961

福祉イノベーション支援プロセスに関して英国ウェールズの使節団との国際交流会を行いました。

2025/6/5 D2の野村彩乃さんが、日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025においてRobomech表彰(研究学術分野)を受賞しました。

研究発表(ロボティクス・メカトロニクスに関する国内会議)
M2の泉谷さん、能崎さん、半田さん, B4の稲垣さんが、日本機械学会・ロボメカ2025で発表を行いました。
-
稲垣賢, 佐野直樹, 大野美喜子, 山中龍宏, 橋本優生, 西田佳史, "睡眠環境安全のための画像を用いた乳幼児の睡眠移動の理解," 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025予稿集, pp. 1P1-Q01, 2025
-
能崎直紀, 川辺有哉, 佐々木駿輔, 山中龍宏, 西田佳史, "生活状況に埋め込み可能なデザインの支援" 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025予稿集, pp. 1P1-Q02 , 2025
-
泉谷颯哉, 橋本優生, 大野美喜子, 佐野直樹, 西田佳史, "深部体温変化の非接触計測法の基礎検討," 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025予稿集, pp. 2A2-M01, 2025
-
半田慧, 野村彩乃, 栗林詩歩未, 北村光司, 河合恒, 西田佳史, "フレイル高齢者支援を目的とした生活環境における小さな形状変化が身体保持性に与える効果の解析," 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025予稿集, pp. 2A1-A05 , 2025


研究発表(人工知能・理学療法に関する国内・国際会議)
M1の川辺さん、特別研究員の栗林さんが研究発表を行いました。
-
Shihomi Kuribayashi, Naoki Sano, Shunji Oya, Yasuhiro Sueshige, Moegi Tsuta, Arata Nishikatsu, Koji Kitamura, Hiroyuki Hagiwara, Yoshifumi Nishida, "Enhancing well-being through the new city-research institute partnership platform to promote the welfare industry in Kawasaki City," Proc. of the World Physiotherapy, G6-102-131, 2025
-
大野 美喜子, 吉成 花恵, 野村 彩乃, 西田 佳史, 河合 恒, "Willingness to Expose: 生活空間における見守り技術に関するデータ暴露意思とサービスとの関係理解, " 第39回人工知能学会全国大会予稿集, pp. 4L1-OS-36-04, 2025
-
川辺 有哉, 能崎 直紀, 佐々木 駿輔, 大野 美喜子, 北村 光司, 西田 佳史, "日常生活の行動と環境を考慮可能なリスクアセスメント手法, " 第39回人工知能学会全国大会予稿集, pp. 4L1-OS-36-05, 2025



新人歓迎会(2025/5/22)
新メンバーとともに恒例の手作り料理(餃子、つくね、スイーツ)による新人歓迎会を行いました。

新しいメンバーの参加。
M1 羽根さん、行平さん、B4の田中さん、徳富さん、松元さんが新たなメンバーとして加わりました。


最近の成果(論文の掲載)
深部体温推定技術(深部体温センサの軽量化と高精度化の両立に関する技術, 深部体温センサのマルチモーダルセンサ化に関する技術)に関する成果が国際ジャーナルに掲載されました。
-
Y. Hashimoto, S. Tada, and Y. Nishida, "Lightweight Probe Cover for Wearable Thermal Device Designed Through Topology Optimization," IEEE Access, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3561285
-
Y. Hashimoto, K. Noto, S. Tada, and Y. Nishida, "Wearable Multimodal Sensor Probe for Monitoring Core Body Temperature, Electrocardiogram, Heart Rate, and Sweat Rate," IEEE Access, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3561288

受賞のお知らせ
佐々木さん(M2)が、ESDコース・自動車技術会大学院奨励賞を受賞しました。川辺さん(B4)機械系優秀学生賞を受賞しました。稲垣さん(B4)、髙木君(B4)が、白星会機械系優秀発表賞を受賞しました。

卒業おめでとう。
M2の大澤さん、佐々木さん、篠澤さん、吉成さん、B4の稲垣さん、川辺さん、髙木さん卒業おめでとうございます。
.jpg)
受賞のお知らせ(計測自動制御学会ユニバーサルデザイン応用システム部会UDXワークショップ2025 UDX賞)
2025年2月17日に開催された計測自動制御学会・ユニバーサルデザイン応用システム部会・UDXワークショップ2025の発表に関して、D1の野村彩乃さんがUDX賞を受賞しました。(対象発表:野村 彩乃,西田 佳史, 「ポータブルな全日常空間身体保持力ベクトル場の計測・可視化技術」)

研究発表(国際ジャーナルへの掲載)
深部体温を計測可能にする技術がIEEE Sensors Lettersに掲載されました。10月に開催されるIEEE Sensors 2024にて発表予定です。
-
Y. Hashimoto, S. Tada and Y. Nishida, "Reference-free calibration for wearable core body temperature sensor based on single heat flux method," IEEE Sensors Letters, 2024 (in press) (https://doi.org/10.1109/LSENS.2024.3435965)

研究発表(国際ジャーナルへの掲載)
画像処理を用いた力センサがIEEE Sensors Lettersに掲載されました。10月に開催されるIEEE Sensors 2024にて発表予定です。
-
Ryuichi Ikeya, Yoshifumi Nishida, ”Force Distribution Sensor Based on Externally Observable Three-Dimensional Shape Deformation Information, " IEEE Sensors Letters, Vol. 8, No. 8, pp. 1-4, 2024 (https://doi.org/10.1109/LSENS.2024.3423656)

川崎ウェルテックの展示会
3/15の川崎ウェルフェアイノベーションフォーラムで開発製品が展示されました。
23/9/28 日本学術会議から子どもの事故予防に関する見解が公開されました。
日本学術会議臨床医学委員会・心理学・教育学委員会・健康・生活科学委員会・ 環境学委員会・土木工学・建築学委員会合同子どもの成育環境分科会が作成した見解『こどもの傷害を減らすためのデータ収集および利活用の促進』が公開になりました。

23/9/16 に日本学術会議主催シンポジウム 『動き出す、こどもまんなか安全社会』を開催しました。
事故による子どもの傷害は多発しており、傷害データを活用し、子どもの傷害の数を減少させる仕組みの構築が急務となっています。日本学術会議・子どもの成育環境分科会では、見解(案)「こどもの傷害を減らすためのデータ収集および利活用の促進」を取りまとめました。本シンポジウムでは、見解(案)で示す目指すべき社会像と、その社会像の実現に向けて動き出している新たな取り組みを紹介します。課題の指摘にとどまることなく、国や地域で始まっている新たな胎動を参加者と共有すること、また、今後、社会実装を進める上での関係者間のネットワークづくりを促進したいと考えています。詳しくはこちらから。
当研究室では、見解(案)の基礎となる技術開発にこれまで関わってきましたが、いよいよ社会実装に向けて動きだします。
当日の様子はこちらの動画をご覧ください。
社会実装・地域連携プロジェクト
川崎市、産業技術総合研究所との共同プロジェクト「川崎ウェルテック」が2021/8/31からスタートしました。最新の成果を盛り込んだ動画に更新しました(2025/9/8)。
研究テーマ:人間中心から生活中心へ機械システムの統合原理を拡張する生活セントリックデザイン
人生100年時代の到来により、高齢者か子どもなどの生活機能が変化する人たちが、健康で安全に、そして、高度な社会参加を可能とする社会の構築(生活機能レジリエント社会*)が求められています。健康、安全、参加等の問題は、いずれも、現在は、個人の努力の問題として扱われていますが、実際には、個人の手に負えない問題ばかりです。
手に負えない社会問題解決のためには、対象となる人間だけに注目するのではなく、課題が発生している実際の生活の場を含めた生活システム全体で人間を理解することが必要です。そのうえで、状況を手に負える化するための新たな人工物を、実際に機能している生活システムへと統合することで、生活システムを拡張する方法論が不可欠です。生活セントリックデザインでは、生活状況を計測し、計算し、デザイン可能にする技術体系の創造をめざし、以下のような研究テーマに取り組んでいます。
形状計測時代にマッチした新たなセンサ化原理(Sensorization of deformable things):1990年代からセンサを埋め込むユビキタスコンピューティング技術、もしくは、同様の概念がIoTと呼び名を変えて発展してきました。一方、最近、安価なデプスカメラと機械学習の発展によって、日用品の形状変形情報から人間の活動を計測する新たなセンサ化技術が可能になりつつあります。センサ埋め込みの方法ではない今後の新たな流れとして、形状計測時代が射程とする新たなセンサ化、IoT化技術を開発しています。
非エルゴ―ド的人間理解技術(生活状況観察・理解技術):従来は、ラボや専門機関で短期的に多人数でデータを集めることで、集合平均=時間平均というエルゴ―ド的人間理解の研究が数多くなされてきましたが、感度が高い変化の検出が困難でした。しかし、IoTに発展によって、個人の長期の時系列データ計測を行い、感度の高い個人内変化の検出が可能になりつつあり、この新しい原理に基づいた生活理解技術を開発しています。
ビヘービアベースド生活理解技術(生活状況観察・理解技術):在宅環境でも環境の形状データ、姿勢データ等が取得可能になっています。姿勢認識・行動認識を前提とした、あるいは、事前に認識すべき対象が明確ではない行動に対して、教師無しで分類を行うことで理解するビヘービアベースドなアプローチが可能になっており、生活理解・生活支援技術に大きな変革をもたらしつつあります。乳幼児や認知症高齢者などに対して、こうした新たなビヘービアベースドアプローチを用いた生活理解技術の開発を進めています。1980年代に隆盛した包摂アーキテクチャーのロボットモジュール的ビヘービア、2000年代の行動経済学の心理的ビヘービアとは異なり、観察可能な行動現象から日常生活現象の理解やモデリングを進める新たなアプローチを目指しています。
状況の数理技術(生活状況という系を扱う数理技術):テキスト情報から得られる状況の意味論的ビッグデータ, センサから得られる状況の物理現象的データを活用し社会現象および物理現象の両方から人間の生活状況を観察可能にする技術や、これらの観察データから状況の全体像の理解、介入すべき状況の抽出、状況の再現や予測を可能とする技術を開発しています。文字、画像、動画というこれまでの多次元マルチメディアの方向だけではなく、環境と人からなる系の構成要素自体が変化する系を扱う方法論が求められています。
事例工学(Episode Engineering)技術:以前は、紙の大きさに情報が制約された時代がありました。例えば、知識伝達は、A4サイズの紙1枚以内とか両面で収まるようになどという時代がありました。そのため、専門家しか分からない、場合によっては、専門家でも分からないような抽象的な表現が取られていましたが、電子化の普及により情報媒体が大きく変化しています。知識表現それ自体が変わりつつあります。分厚い事例(エピソード)のデータベースがあり、それを状況に合わせて巧みに検索できるような形態の知識も現場に役立つ新たな情報提示であり、具体化困難な抽象的表現の問題の解決に繋がる可能性があります。
生活レイヤに踏み留まる生活シミュレーション技術:以前から、そして、今なお、機械工学では、有限要素解析技術をはじめとする物理的シミュレーション技術がよく利用されていますが、人を含んだ生活機械システムのモデリングやシミュレーションは未だよいものが存在しません。これは、支配方程式がないからです。そのため、そのような方程式が存在するミクロ側かマクロ側へと展開され、逆に、生活からどんどん遠ざかる方向へと研究が展開されがちになります。上述した、非エルゴ―ド的理解、ビヘービアベースド理解、状況数理技術、事例工学などを有機的に結びつけて、生活を計算可能なシミュレーションの開発を進めています。
リアルな生活条件下で機能する技術のための生活システム統合技術:社会実装をAttitudeの問題(寄り添いの問題)だけに帰着させないためには、そのための方法論が大切です。実際の生活環境で機能する際に最も重要なことは、実際の生活条件をよく知ることです。リアルな生活条件下で実際に機能する生体計測技術(ex., 深部体温推定)など、行動モデル、バイオメカニカルモデル、心理モデル、生活状況モデルを生活システムとして統合する研究を進めています。
Empowering Reality技術(生活デザイン技術):一般家庭、保育所、介護施設などの生活の場をデザイン可能にするためには、従来のように、課題に対応した様々な提案を行うだけでは不十分で、それらの提案が実際の生活場面で受け入れらない本当の理由に関する膨大なデータを取得し、その困難世界を乗り越えるための提案が不可欠です。こうした困難データ(不可能世界)の収集や、エンパワメント(可能化支援)のための情報提示技術や機械システムの研究を行っています。
これらの研究を、傷害予防学研究会(Childhood Injury Prevention Engineering Council)、産業技術総合研究所、東京都健康長寿医療センター、日本スポーツ振興センター、東京消防庁、東京都、神奈川県川崎市、厚木市、秩父市、長崎県大村市との多職種連携体制で研究を推進しています。
(*)生活機能レジリエンスとは、ロボット、AI、社会サービスなどによって、心身機能が変化しても、なお、健康で安全に社会参加ができる状態へと支援していくれることを意味しています。

生活状況センシング技術
暑熱対策向けウェアラブルセンサ
熱中症対策に向け、活動中の暑熱リスクの把握に有益な生理指標である深部体温、心拍数、発汗量を計測するウェアラブルセンサの開発を基礎・応用の両面から進めています。
-
Hashimoto Y, Ishihara T, Kuwabara K, Amano T, Togo H (2022), “Wearable Microfluidic Sensor for the Simultaneous and Continuous Monitoring of Local Sweat Rates and Electrolyte Concentrations,” Micromachines, vol. 13, No. 4, 575, doi: 10.3390/mi13040575.
-
Hashimoto Y, Sato R, Takagahara K, Ishihara T, Watanabe K, Togo H (2022), “Validation of Wearable Device Consisting of a Smart Shirt with Built-In Bioelectrodes and a Wireless Transmitter for Heart Rate Monitoring in Light to Moderate Physical Work,” Sensors, Vol.22, No.23, 9241. DOI: 10.3390/s22239241.

身体保持力場の全空間マッピング
ウェアラブルセンサと姿勢認識機能を組み合わせ、いつ、どこで、体をどのように支えているのかという身体保持力場の解明のための新たな計測・分析技術を開発し、生活機能レジリエントなプロダクトデザインへの展開する研究を行っています。
-
Ayano Nomura, Yoshifumi Nishida, "Visualization of Body Supporting Force Field of the Elderly in Everyday Environment," Proc. of IEEE International Conference on Sensors, 2022

在宅階段手すり型IoTセンサを用いた複数人の高齢者の昇降特性理解
階段手すりに埋め込まれたセンサから歩行速度や把持ダイナミクスの長期トレンドを分析可能にする技術を開発しています。
-
Moe Hamada, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, “Ambient understanding of stairway ascension and descension by the elderly using a handrail-based force sensor.” Procedia Computer Science, Vol. 177, pp. 405-414, 2020

バッテリレス靴型位置センサを用いた認知症高齢者モニタリング
歩行時に発生する足裏の力変化を活用し、電池なしで位置を追跡可能にする技術を開発しました。
-
Kazuya Takahashi, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, Hiroshi Mizoguchi, "Battery-less shoe-type wearable location sensor system for monitoring people with dementia," Proc. of the 13th International Conference on Sensing Technology, pp. 12-15, December 2 2019 (Macquarie University, Sydney, Australia) (Best Paper Award)

Vision-based Force Sensor
安価なデプスカメラと機械学習を活用し、日用品の形状変形情報から人間の活動を計測可能にする新たな力センサ技術を開発しています。
-
Ryuichi Ikeya, Yoshifumi Nishida, "Visual Force Sensor to Estimate External Force Distributions from Shape Deformation," Proc. of IEEE International Conference on Sensors, 2023
-
Ryuichi Ikeya, Yoshifumi Nishida, ”Force Distribution Sensor Based on Externally Observable Three-Dimensional Shape Deformation Information, " IEEE Sensors Letters, Vol. 8, No. 8, pp. 1-4, 2024

生活状況理解技術(状況数理技術・非エルゴ―ド的人間理解技術)
ビッグデータを用いた状況リスク可視化
リスク要因として「状況(コンテクスト、プロセス)」を計算可能にする手法を開発しました。疫学的手法とテキストデータの分散表現技術を融合することで、典型的かつ重要な状況を可視化する技術を開発しています。状況R-Map手法は、学校現場のリスク分析に利用されています。
-
Masaaki Ozaki, Yoshifumi Nishida, Tatsuhiro Yamanaka, "Prioritizing Injury Situation to be Prevented Based on AI-Aided Situational R-Map," Injury Prevention, Vol. 28, supple 2, 2022

高齢者の生活支援のためのフレイル早期発見や身体機能変化検出を可能とする非エルゴ―ド的人間理解
高齢者リビングラボ(在宅環境)による個人の長期間の在宅データを用いて、身体機能の微細な変化を捉える非エルゴ―ド的人間理解のための新たなセンシング技術、および、データサイエンス手法を開発しています.
-
Moe Hamada, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, "Individual and longitudinal trend analysis of stairway gait via ambient measurement using handrail-shaped force sensor," IEEE International Conference on Sensors, 2021

ビヘービアベースドな乳幼児発達行動診断
行動を直接認識対象とすることにより,高精度な発達段階推定を可能とする新たなビヘービアベースドな診断手法を開発しています。
-
Yoshifumi Nishida, Kento Komori, Miho Nishizaki, "Automated Infant Developmental Stage Estimation Method Using Image Processing and Denver II," Injury Prevention, Vol. 28, supple 2, 2022

データ駆動型乳幼児よじ登り行動シミュレーション
従来、運動能力・認知能力が複雑に絡む、子どものよじ登り行動をシミュレーションする技術は存在していません。よじ登り行動データベースから予測する技術を開発しています。
-
Tsubasa Nose, Koji Kitamura, Mikiko Oono, Michiko Ohkura and Yoshifumi Nishida, "Data-driven Child Behavior Prediction System Based on Posture Database for Fall Accident Prevention in a Daily Living Space," Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020

生活状況デザイン技術
Empowering Reality技術
新しい技術が使われない理由を考慮しながら、その個人が技術を使っている状態へと変化させてくれる技術Empowering Reality技術の開発を行っています。コロナ禍で急速に普及した遠隔会議技術と、画像処理・AR技術・状況グラフ技術を統合し、一般家庭、保育所、高齢施設等の仮想訪問時にその場で状況デザインを支援する技術を検証しています。
-
Mikiko Oono, Thassu Srinivasan Shreesh Babu, Yoshifumi Nishida, Tatsuhiro Yamanaka, "Empowering Reality: A New Injury Prevention Education System to Promote the Empowerment of Child Caregivers," The International Journal of Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (JUSPN) , Vol. 18 , Issue 1, pp. 01 - 08, 2023

生活機能レジリエントデザイン
生活機能の変化に対してシームレスな自生活機能低下者には、福祉用具という従来の考え方からのパラダイムシフトを狙いとして、立支援となる新たなデザインを提案しました。
-
Mikiko Oono, Ayano Nomura, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, Shunsaburo Nakahara, Hisashi Kawai, "Homeostatic System Design Based on Understanding the Living Environmental Determinants of Falls," Proc. of the IEEE International Conference on System, Man, and Cybernetics, 2023

免疫学を応用したリスク制御システム
日々出現する多様な危険源にうまく対応している生体機能に免疫があります。病原体に対して免疫が持っている「抗原の多様性に対する予防機能の特異性」を情報学の観点から再現し、生活環境下の致死性状況の対応へと応用した「リスク免疫情報システム」の開発を進めています。

疫学と現場データを統合した生活環境適合型リスク管理システム
疫学と現場の傷害発生状況が類似したものを抽出することで今後起こりうる事故のうち,対策を優先すべき事例をVR/メタバース空間に提示するアルゴリズムを開発しています。
-
Shunsuke Sasaki, Mikiko Oono, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, "An Assistive Technology for Equitable Home Safety Based on Situational Risk and the Bio-Psycho-Social Model," The Proc. of 2024 IEEE Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), 2024

目指す研究活動・研究者像

社会と相互作用するデザイン
現場のディテールを観察することで、生活機能の構造的・定量的理解に基づいて問題構造を見つけ、社会的な問題として表出させ、現実的なソリューションを機械工学・情報工学等の知識を活用し、地域社会と生活者の制約条件を満たしつつ、多職種連携で開発し、持続可能な社会システムとして根付かせるまでの一貫した活動が推進できる技術者・研究者の育成

生活セントリックデザインラボの7つの原則
-
現実問題・ニーズに対峙せよ.
-
具体的な課題・本当にある問題を扱え.現実の世界は,基礎的な科学研究を導くよい研究課題の,もっとも豊かな土壌.(by Herbert A. Simon)
-
-
社会を変える具体的なストーリを作れ.
-
技術が実際に役立つまでをコンプリート(一貫)させるシナリオを作れ. (by 金出武雄先生)
-
-
土台・土俵が無ければ,そこから作れ.
-
「未整備」と指摘するだけではなく、「未整備」を克服する方策を考えろ.野党ではなく、与党になれ。
-
-
明日の常識・理論を作れ.
-
現実問題の解決に役立つ理論を目指せ.将来, 当たり前となる常識を待ち構えて作れ(by 佐藤知正).技術がグロテスク化したら学術病を疑え.テーマを見直せ.
-
-
複雑系は,複雑系で解け.
-
解きたい対象が複雑系であれば,解く体制も複雑系で取り組め.
-
-
ユーザ指向で完成度の高い技術まで極めよ.
-
実用はゴールではなく,スタートと考えよ. 実用されることでしか,手に入らないデータがあり、そこからしか始まらない科学がある.実用は大きな価値.
-
-
知的好奇心から「知的解決心」へ.
-
社会問題の解決は,制約条件を考慮しつつ,技術体系・社会体系の総力で解く極めて知的な活動.
-
SDGsの観点

SDGsで示されている社会課題は、そのままでは操作できない社会次元(具体性が捨象されたマクロな次元)の問題です。これを,生活次元での詳細な把握をもとに(生活現象というミクロな次元への生活次元展開),操作可能な状態へと問題構造を変化させられる技術体系を目指しています.
研究室の問い合わせ・交通アクセス
研究にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。研究内容や出版物に関するご意見やご質問は、どうぞお問い合わせください。